「あの人って、なんでいつもネガティブなことばかり言うんだろう?」と思ったことはありませんか? 周囲にいるネガティブな人の発言を聞いていると、こちらまで気分が落ち込んでしまうこともありますよね。ネガティブな発言をする人には、実はさまざまな心理的な理由があります。
本記事では、ネガティブな発言をする人の心理を深掘りして行きます。
ネガティブな発言をする人の心理とは?

防衛本能としてのネガティブ思考
人は本能的に危険を回避するために、ネガティブな考えを持つことがあります。これは、進化の過程で生き延びるために必要だった機能です。例えば、「この食べ物を食べたら毒かもしれない」「この道を進んだら危険かもしれない」といった警戒心は、命を守るために重要でした。
現代社会においても、この防衛本能が強く働く人は、無意識にリスクを避けるためにマイナスな発言をしがちです。「この仕事は失敗するかもしれない」「そんなことをしても意味がない」といった言葉が出るのは、危険を避けるための自己防衛の表れとも言えます。
しかし、過度なネガティブ思考は、行動を抑制し、チャレンジの機会を奪うことにもなります。例えば、新しい仕事に挑戦する際に「失敗するかも」と思って行動しなければ、成長の機会を失ってしまうのです。
このような思考パターンを持つ人には、リスクを回避する意識が強いことを理解したうえで、「やってみないとわからないよ」とポジティブな視点を提案することが効果的です。
承認欲求と注目を集めたい心理
ネガティブな発言をする人の中には、周囲の関心を引くためにそうした発言をする人もいます。「大変だった」「最悪だった」「疲れた」などの言葉を頻繁に使う人は、自分の話に共感してもらい、慰めてもらいたいという気持ちが強いことがあります。
例えば、仕事で失敗した際に「もうダメだ」と口にする人は、実は「そんなことないよ」「大丈夫だよ」と言ってもらいたいのかもしれません。ネガティブな言葉を発することで、周囲の人に自分の存在を認めてもらい、安心感を得ようとしているのです。
このタイプの人には、必要以上に共感しすぎると、さらにネガティブ発言が増えてしまうこともあります。「大変だったね」と共感しつつも、「次はこうするといいかもね!」と前向きなアドバイスを加えると、徐々にネガティブ発言が減っていく可能性があります。
過去の経験が影響しているケース
人は過去の経験によって、考え方や発言の傾向が変わります。特に、過去に辛い経験や挫折をした人は、同じような失敗を繰り返したくないという気持ちから、慎重になりがちです。その結果、物事を悲観的に捉えるクセがついてしまうことがあります。
例えば、過去に人間関係で裏切られた経験がある人は、「どうせまた裏切られる」と考え、人との距離を取るようになります。仕事で大きなミスをしたことがある人は、「また失敗するかもしれない」と不安になり、新しいチャレンジを避けようとします。
こうした人には、無理にポジティブ思考を押しつけるのではなく、まずは過去の経験を理解してあげることが大切です。「そういう経験があったんだね。でも、今の状況は違うかもしれないよ」と、過去と現在を切り離して考えられるような声かけをすると、少しずつ前向きになれるかもしれません。
性格や気質が関係している可能性
人にはそれぞれ生まれ持った性格や気質があり、ネガティブな発言をしやすいタイプの人も存在します。例えば、慎重派の人や完璧主義の人は、リスクを避けるために、ネガティブな発言をする傾向があります。
また、HSP(Highly Sensitive Person)のように、感受性が強く、周囲の環境に敏感な人は、ちょっとしたことで不安を感じやすくなります。そのため、「こんなことを言ったら嫌われるかも」「失敗したらどうしよう」と考え、ついネガティブな発言をしてしまうのです。
こうした性格の人には、「慎重なのは良いことだね」「でも、ちょっと視点を変えてみるとどうかな?」と、肯定的に受け止めつつも、別の考え方を提案するのが効果的です。
ストレスや不安が原因の場合
ネガティブな発言が増える背景には、ストレスや不安が大きく関係していることもあります。仕事が忙しい、家庭での悩みがある、将来の不安を抱えているなど、精神的な負担が大きいと、人は自然とマイナス思考になりがちです。
例えば、仕事でプレッシャーを感じている人は、「どうせうまくいかない」「もう無理だ」とネガティブな言葉を発しやすくなります。また、家庭の問題を抱えている人は、周囲の人に対してもイライラしやすく、つい否定的な発言をしてしまうことがあります。
この場合、相手のネガティブ発言に振り回されるのではなく、「最近疲れてるのかな?」と気遣いの言葉をかけることで、少し心を開いてもらえるかもしれません。また、相手がリラックスできる環境を作ることも、ネガティブ発言を減らすのに役立ちます。
ネガティブな発言をする人には、さまざまな理由があることがわかりました。次の章では、ネガティブな発言がもたらすメリットやデメリットについて詳しく見ていきます。
ネガティブな発言をすることで得られるメリット?

共感を得ることで安心する心理
人は誰しも、他人に理解されたいという欲求を持っています。ネガティブな発言をすることで、周囲から「大変だったね」「つらかったね」と共感してもらえると、安心感を得ることができます。これは、人間関係の中で自然に生まれる心理的な欲求の一つです。
例えば、「仕事が大変すぎてもう無理」と言う人は、「そんなに大変なんだね」「無理しないでね」と言われることで、自分の気持ちを理解してもらえたと感じます。特に、悩みやストレスを抱えているときは、誰かに気持ちを分かってもらうことが精神的な支えになるのです。
しかし、ネガティブな発言を続けると、周囲の人も次第に疲れてしまいます。最初は共感してくれていた人も、「またか…」と感じるようになり、距離を取られることもあります。そのため、ネガティブな発言をする人は、他人に共感を求めすぎないように注意する必要があります。
自己防衛の手段として使う場合
ネガティブな発言をすることで、リスクを回避しようとする人もいます。たとえば、「どうせ失敗する」「自分には無理」と言うことで、挑戦する前から傷つくことを避けようとするのです。
これは、過去に大きな失敗を経験した人や、完璧主義の人に多い傾向があります。完璧を求めるあまり、「うまくいかないかもしれない」と不安になり、最初から諦めることで自分を守ろうとします。
このような場合、周囲の人が「大丈夫だよ!」「やってみようよ!」と励ましても、本人の不安は消えません。それどころか、「どうせ自分にはできないのに…」と、さらに落ち込んでしまうこともあります。
このタイプの人には、「もし失敗しても大丈夫」という安心感を与えることが重要です。「失敗しても学びになるよ」「まずは小さなことから試してみよう」と声をかけることで、少しずつ前向きな気持ちになれるかもしれません。
人間関係の主導権を握ろうとする心理
ネガティブな発言をすることで、周囲の人をコントロールしようとするケースもあります。例えば、「どうせ私なんて…」「あなたがいないとダメなんだ」と言うことで、相手に助けてもらおうとする人もいます。
このような発言を繰り返すと、周囲の人は「この人を支えなきゃ」と感じ、ネガティブな発言をする人に気を遣うようになります。すると、結果的にその人が人間関係の主導権を握ることになるのです。
このタイプの人に対しては、必要以上に相手の言葉に振り回されないことが大切です。「それは大変だね」と共感しつつも、「でも、自分でできることもあるんじゃない?」と少しずつ自立を促すような言葉をかけると、関係が健全になります。
責任を回避するための言い訳としての利用
ネガティブな発言をすることで、自分の責任を回避しようとする人もいます。例えば、「どうせやっても無駄」「誰も分かってくれない」と言うことで、行動しない言い訳を作るのです。
これは、仕事や勉強などでプレッシャーを感じたときに特に多く見られます。「どうせ頑張っても評価されない」「無理にやっても意味がない」と考えることで、努力しない理由を作り、責任から逃れようとするのです。
このような場合、「本当に無駄なのか?」と問いかけることで、考え方を変えるきっかけを作ることができます。また、「小さなことから始めてみよう」と提案すると、少しずつ行動できるようになることもあります。
自分を正当化する手段としてのネガティブ発言
最後に、ネガティブな発言をすることで、自分の立場を正当化しようとするケースもあります。例えば、「私は運が悪いから」「どうせ才能がないから」と言うことで、努力しないことを正当化するのです。
このような人は、自分に自信がないことが原因でネガティブな発言をしている場合が多いです。過去の経験から「どうせ頑張ってもダメ」と思い込んでしまい、自分の可能性を否定してしまっているのです。
このタイプの人には、「本当にそうなのか?」と冷静に問いかけることが有効です。「前にうまくいったことはなかった?」とポジティブな事実を思い出させることで、考え方を少しずつ変えていくことができます。
ネガティブな発言をすることで得られるメリットはありますが、長期的に見ると、デメリットの方が大きいことが分かります。次の章では、ネガティブな発言が多いとどのような影響があるのかを詳しく解説します。
ネガティブな発言が多いとどうなるのか?
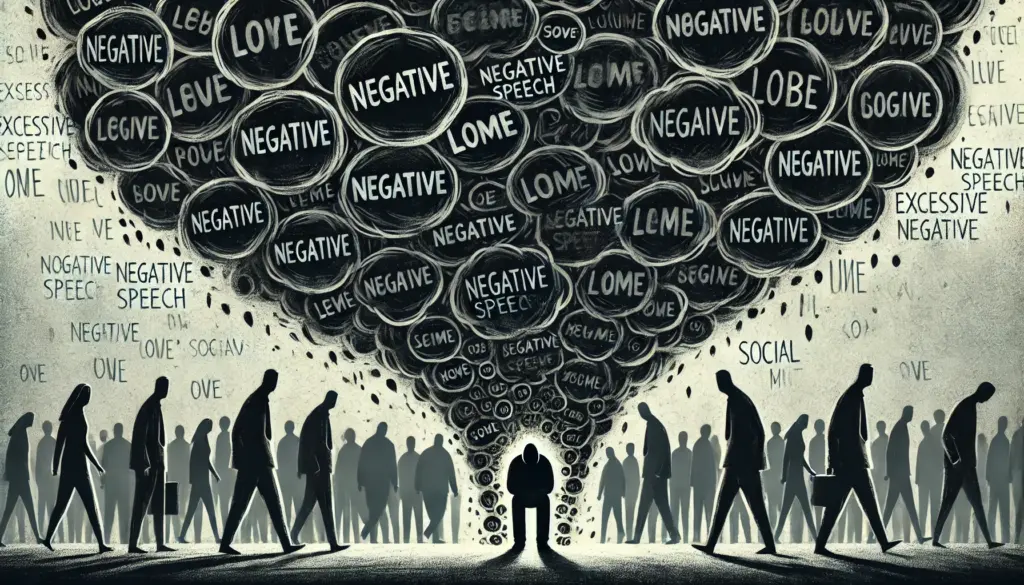
周囲の人に与える影響
ネガティブな発言が多いと、周囲の人にも悪影響を与えることがあります。たとえば、職場で「このプロジェクトはうまくいかない」「やっても意味がない」といった言葉を頻繁に聞かされると、他のメンバーのモチベーションも下がってしまいます。
心理学では「感情伝染」という現象があり、人は無意識のうちに周囲の感情に影響を受けることが分かっています。ネガティブな言葉を聞き続けると、それを聞いた人の気持ちも暗くなり、結果的に全体の雰囲気が悪くなってしまうのです。
また、家庭でも同じことが言えます。例えば、親が「お金がない」「将来が不安」といったネガティブな発言を繰り返すと、子どもも不安を感じやすくなります。これは、親の言葉が子どもの価値観に影響を与えるためです。
こうした影響を防ぐためには、ネガティブな発言が多い人に対して適度な距離を保つことが大切です。また、「でも、こういう良い点もあるよね」とポジティブな視点を示すことで、空気を変えることができます。
仕事や人間関係でのデメリット
ネガティブな発言が多いと、仕事や人間関係にも悪影響が出ます。特に、職場では次のような問題が発生することがあります。
- 周囲からの信頼を失う
ネガティブな発言ばかりしていると、「この人と一緒にいると気分が下がる」と思われ、周囲から距離を取られてしまうことがあります。 - チャンスを逃す
「どうせ無理」「やっても意味がない」と考えることで、新しい挑戦を避けてしまい、成長の機会を逃してしまいます。 - 仕事の効率が下がる
「どうせ失敗する」と思いながら仕事をすると、やる気がなくなり、結果としてパフォーマンスが下がることがあります。
人間関係でも、ネガティブな発言が多いと、「この人と話すと疲れる」と思われ、友人や同僚が離れていくことがあります。反対に、ポジティブな言葉を使う人は、周囲の人から好かれやすくなります。
自分自身のメンタルへの悪影響
ネガティブな発言は、言葉にした本人のメンタルにも影響を与えます。心理学では「自己成就予言(セルフ・フルフィリング・プロフェシー)」と呼ばれる現象があり、「自分はダメだ」と思っていると、本当にその通りの結果になりやすいことが分かっています。
例えば、「試験に落ちるかも」と思って勉強していると、不安で集中できず、本当に試験に落ちてしまうことがあります。また、「私は人に嫌われる」と思っていると、無意識に人と距離を取るようになり、本当に孤立してしまうのです。
このように、ネガティブな発言は、最終的に自分自身の行動や考え方に影響を与え、悪循環を生み出すことがあります。そのため、できるだけポジティブな言葉を意識することが大切です。
ポジティブな人が離れていく可能性
ネガティブな発言を続けていると、ポジティブな考えを持つ人が自然と離れていくことがあります。ポジティブな人は、明るく前向きな環境を好むため、ネガティブな発言が多い人と一緒にいると、ストレスを感じやすくなります。
例えば、職場で「この仕事は無理」「どうせ評価されない」といった言葉ばかり発する人がいると、前向きに頑張ろうとしている人は「なんでそんなにネガティブなの?」と感じ、距離を置くようになります。
また、友人関係でも、ネガティブな話題ばかり話す人は、「会うと疲れる」と思われ、徐々に誘われなくなってしまうことがあります。ポジティブな人と良い関係を築くためには、できるだけ前向きな話題を意識することが重要です。
ネガティブ思考が習慣化する危険性
最後に、ネガティブな発言を続けることで、それが習慣になってしまう危険性があります。人間の脳は、繰り返し使う思考パターンを強化する性質があるため、ネガティブな言葉を使い続けると、自然とネガティブな考えが定着してしまうのです。
例えば、「自分はダメだ」「どうせ無理」といった言葉を繰り返していると、それが当たり前の考え方になり、何をするにもネガティブに捉えるようになってしまいます。
これを防ぐためには、普段の言葉遣いを意識することが大切です。「できない」ではなく「どうすればできるか?」と考える習慣をつけるだけでも、思考パターンがポジティブに変わっていきます。
ネガティブな発言をする人には、さまざまな理由があります。防衛本能としてリスクを避けようとする心理や、承認欲求から共感を求めるケース、過去の経験や性格による影響などが挙げられます。また、ネガティブな発言をすることで、周囲の注目を集めたり、責任を回避したりするメリットがあると感じる人もいます。
しかし、ネガティブな発言が多くなると、周囲の人に悪影響を与えるだけでなく、本人のメンタルにも悪影響を及ぼします。仕事や人間関係に悪影響を与え、ポジティブな人が離れていく原因にもなりかねません。
ネガティブ発言は悪影響しかありません。
ネガティブな発言を極力抑えて、周囲の人にも自分自身にも良い影響を与えていける行動を心掛けて行きたいものですね!


